William Caxton カクストンの悩み1476年にウェストミンスター寺院の敷地内にてイングランド最初の印刷を開始したカクストン。彼の技術によってより多くの人々が読み、書く機会を得たことで英語の発達に大きく貢献しました。英語の「標準化」が実現し、表記ルールも確立し、広く一般に浸透していきました。同じ出版物が大量に流通する「印刷」という技術革新により、より多くの作品が現在にまで残され、当時の様子を知ることができる貴重な資料となっているわけです。カクストンは言語学者でもなければ文学者でもなく、今でいうビジネスマンだったわけですが、ベルギーに30年近くも住んでおり、初期の作品のほとんどがフランス語やオランダ語からの翻訳物でした。しかし、そんな彼にも悩みがあったのです。その悩みとは、実際に翻訳にあたってさっそく抱くことになる「疑問」の数々だったようです。
さて、そのカクストンの悩みですが、まず、上にご紹介しているのは、ある翻訳本の冒頭に彼が書いた前書きです(右のテキストは現代英語に置き換えたものです)。どんなことを書いているのかざっくり読んでみると… などと困り果てている様子がうかがえます。ともあれ、すべての人を満足させるのは至難の技だ、と彼の悩みは続きます。 ●翻訳先の英語にはどこの地域の言葉を使うか?こんなに違うと、もうどうしたらいいのか… ●文体はどんなものにしたらいいだろう?チョーサー風か、トマス・マロリーか、それともラテン語の文学者のものを拝借するか? ●スペルとか句読点の打ち方はどうしよう?歴史的に見ても多種多様… ●英国の作家の作品の場合、もっと多くの人が理解できるように書きなおしたほうがいいのか? などなど。。。 結局彼は(前述のように)文学者ではなく、あくまでもビジネスマン。当然「売れる」ことが大前提。売れるためにはより多くの人が理解できなければ意味がない。しかし、「タマゴ」のような簡単な単語が通じないのに、一体どうやってより多くの人を満足させることができるのか?彼にとっては、いわゆるカスタマー・サティスファクション(顧客満足)も困難の極みだったことでしょう。 さんざん悩んだ(?)カクストンでしたが、決断するのも早いわけです。といっても他の例にならってのことですが、なんとなく世間にもそんな暗黙の了解みたいなものもできつつあって、結局、ロンドン周辺の言葉を使うことに決めました。こうして、ロンドン周辺の方言が標準語として認識されるようになり、それ以外のものは「方言」であるときっぱり線引きがされてくるようになったわけです。100年もすると印刷物はこうあるべき、といった統一性や一貫性が出てくるようになりましたが、一部のスペルやアポストロフィなどの句読点の問題は依然として残され、統一されるには17世紀までかかったようです。 |

|
Last update May 29, 2021
|
|
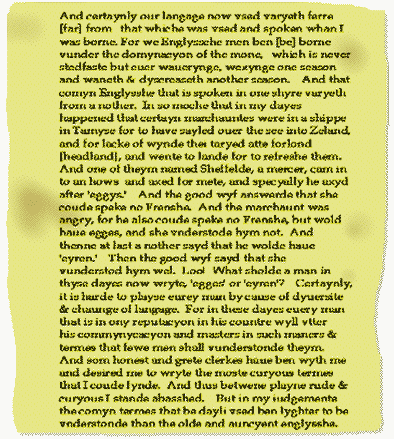 And certainly our language now used varies far from
that which was used and spoken when I was born.
For we Englishmen be born under the dominancy of the moon,
which is never steadfast but ever wavering, wexing one season
and wanes and decreases another season.
And that common English that is spoken in one shire varies from another.
In so much that in my days happened that certain merchants were in a ship
in Thames for to have sailed over the sea into Zeeland,
and for lack of wind they taried at headland, and went to land
for to refresh them.
And one of them named Sheffelde, a mercer, came into a house
and asked for meat, and specially he asked after 'eggs.'
And the good wife answered that she could speak no French.
And the merchant was angry, for he also could speak no French,
but would have eggs, and she understood him not.
And then at last another said that he would have 'eyren.'
Then the good wife said that she understood him well. Look!
What should a man in these days now write 'eggs' or 'eyren'?
Certainly, it is hard to please every man by cause of diversity and change of language.
For in these days every man that is in any reputation in his country will utter
his communication and masters in such manners and terms that few men shall
understand them. And some honest and great clerks have been with me and
desired me to write the most curious terms that I could find.
And thus between plain(?) rude and curious I stand abasshed.
But in my judgement the common terms that is daily used is lighter
to be understand than the old and ancient english.
And certainly our language now used varies far from
that which was used and spoken when I was born.
For we Englishmen be born under the dominancy of the moon,
which is never steadfast but ever wavering, wexing one season
and wanes and decreases another season.
And that common English that is spoken in one shire varies from another.
In so much that in my days happened that certain merchants were in a ship
in Thames for to have sailed over the sea into Zeeland,
and for lack of wind they taried at headland, and went to land
for to refresh them.
And one of them named Sheffelde, a mercer, came into a house
and asked for meat, and specially he asked after 'eggs.'
And the good wife answered that she could speak no French.
And the merchant was angry, for he also could speak no French,
but would have eggs, and she understood him not.
And then at last another said that he would have 'eyren.'
Then the good wife said that she understood him well. Look!
What should a man in these days now write 'eggs' or 'eyren'?
Certainly, it is hard to please every man by cause of diversity and change of language.
For in these days every man that is in any reputation in his country will utter
his communication and masters in such manners and terms that few men shall
understand them. And some honest and great clerks have been with me and
desired me to write the most curious terms that I could find.
And thus between plain(?) rude and curious I stand abasshed.
But in my judgement the common terms that is daily used is lighter
to be understand than the old and ancient english.